

清和天皇―貞純親王―源経基―――源満仲――――源頼信――――源頼義―+―源義家――+―源義親
(兵部卿)(大宰少弐)(鎮守府将軍)(鎮守府将軍)(伊予守)|(陸奥守) |(対馬守)
| |
+―源義綱 +―源義忠 +―源義重―――源義兼
|(美濃守) |(左衛門尉)|(大炊助) (大炊助)
| | |
+―源義光 +―源義国――+―源義康―――源義兼
(甲斐守) |(加賀介) (陸奥守) (上総介)
|
+―源為義――――源義朝―――源頼朝
(左衛門大尉)(下野守) (権大納言)
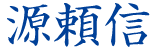 (968-1048)
(968-1048)
摂津守源満仲の長男。幼名は竹童子(『系図編纂』)。通称は不明。母は「陸奥守藤原致忠女」または「大納言藤原元方御女」(『尊卑分脉』)。妻は修理命婦。官は甲斐守(『小右記』長元三年九月六日條)、伊勢守(『左経記』万寿五年六月廿一日條)、常陸介(『今昔物語集』)、上野介(『御堂関白記』長保元年九月二日条)、美濃守(『類聚符宣抄』八 任符事)、河内守。
安和元(968)年(『諸家系図纂』武田)、または天延2(974)年11月29日の誕生(『系図編纂』)と伝わる。
妻の「修理命婦」は父が修理職に務める女官だろう。彼女は仁平4(1151)年3月29日、大外記中原師元が関白藤原忠実邸に祇候した際に「御物語之次仰云」ったことにある。
●『中外抄』下五十三「久安四年記」
頼義ト随身兼武トハ一腹也、母宮仕者也、件女ヲ頼信愛之令産頼義了、其後兼武父、件女ノ許ナリケル半物ヲ愛ケルニ、ソノ主ノ女我ニアハセヨト云テ、如案婚了、其後生兼武了、頼義後ニ聞此旨テ、ユゝシキコトナリトテ、七騎ノ度乗タリケル大葦毛、忌日ナムトヲハシケレドモ、母忌日ハ一切勧修サリケリ、義家母者直方娘也、為義母ハ有綱女也、已華族也(頼義と随身兼武とは一腹の兄弟である。母は宮仕えの者で、この女は頼信が愛して頼義を産ませた。その後、兼武の父はこの女に仕える半物を愛したが、その主の女は(半物に)『我に会わせよ』と言って、兼武の父と予想通りに婚姻し、その後兼武が誕生した。頼義はのちにこの事を聞いて『忌まわしい事だ』と感じ、奥州戦役で大敗して七騎で退却した際の乗馬大葦毛は、忌日に修法したが、母の忌日には一切勧修することはなかった。義家の母は平直方女、為義の母は藤原有網女でともに堂上出身である)
源頼信
(美濃守)
∥
∥――――――源頼義
∥ (鎮守府将軍)
修理命婦
∥
∥――――――中臣兼武―――中臣近友
∥ (左番長) (1034頃-1093)
中臣某
中臣兼武(大中臣兼武)は永承7(1052)年4月22日、賀茂祭に際して「関白随身左番長大中臣兼武、右府随身下毛野公長以上皆着制物…」(『春記』永承七年四月廿二日條)と見える。
寛和3(987)年2月19日の慧心院造堂料の成功により頼信に叙位があり、当時左兵衛尉であった(『小右記』寛和三年二月十九日条)。永承3(1048)年9月1日、七十五歳で卒去(『系図纂要』)とすると、十四歳のときとなる(『尊卑分脈』の六十歳卒去であると誕生以前のこととなるため不可)。
頼信の元服時期については、『系図要纂』によれば永延2(988)年9月18日元服(『系図編纂』)とあるが、その一年前の寛和3(987)年にすでに左兵衛尉在任であることから、元服はさらに前である。また、永延2(988)年は嫡子頼義誕生年とも重なるため、『系図纂要』の記述は不可であろう。
『諸家系図纂』によれば「円融院天元三年正月十一、元服年十三、加冠叔父満政与兄頼光」(『諸家系図纂』武田)とあり、天元3(980)年正月11日当時十三歳であれば、頼信の誕生は安和元(968)年となり、左兵衛尉在任の寛和3(987)年当時は二十歳であることから、時期的には妥当であろう。
●『小右記』(寛和三年二月十九日條)
正暦5(994)年3月6日、京中に盗賊が跋扈する昨今、陣定でその追捕が検討され、中納言顕光卿は左近衛府の仗座に参着すると、大外記三国致貴を召して「京中并国々盗人捜例文進者」(『本朝世紀』正暦五年三月六日条)と指示した。これを請けた致貴は外記局へ戻ると先例を調べて「進件例文」た。これにより、盗賊追捕の官符が出され、予め召していた「武者源満正朝臣、平維将朝臣、源頼親朝臣、同頼信等、差遣出」た(『本朝世紀』正暦五年三月六日条)。これに加えて「六衛府寮相分遣左右」た(『本朝世紀』正暦五年三月六日条)。頼信は叔父の源満政、兄の頼親のほか、平維将といった人々と同様武勇の人として認識されていた。当時21歳である。
この直後に上野介に補任されたとみられ、長保元(999)年9月2日には「上野守頼信、奉馬五疋、一疋田靏料駒也」(『御堂関白記』長保元年九月二日条)と、左大臣藤原道長およびその嫡子田靏(のちの頼通)に馬を献じた。頼信は受領として上野国に赴任しており、『今昔物語集』にその記述がみられる。
●「藤原親孝為盗人被捕質依頼信言免」(『今昔物語集』語第十一)
その後、頼信は常陸介に転任している。補任時期は明確ではないが、寛弘9(1012)年閏10月23日に「前常陸守」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日条)とあるので、寛弘9(1012)年以前に常陸介だったことがわかる。
道長のもとには、寛弘9(1012)年閏10月12日に「陸奥守済家」より馬二疋(『御堂関白記』寛弘九年閏十月十二日條)、閏10月16日に「故兼忠朝臣男維吉」より馬六疋(『御堂関白記』寛弘九年閏十月十六日條)、翌閏10月17日に「上野守維叙」から馬十疋(『御堂関白記』寛弘九年閏十月十七日條)、閏10月21日に「将軍兼光朝臣」より馬二疋(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿一日條)、閏10月23日に「出羽守親平」より馬六疋、夜前に「前常陸守頼信」が馬十疋を献じている(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日條)。
治安3(1023)年8月、鎮守府将軍に補任。
万寿4(1027)年12月4日、朝廷の実力者であった藤原道長が死去しておよそ五か月後の万寿5(1028)年5月頃、下総国の在庁「権介」である平忠常の軍勢が安房国司館を攻めて「安房守惟忠、為下総権介平忠常被焼死了」(『編年残篇』)し、「長元の乱」が勃発した。この平忠常の起こした乱については、「平忠常」を参照。
安房国司焼殺の件につき、6月5日、朝廷は「平忠常并男常昌等可追討宣旨事」(『小記目録』十七 臨時七)と決定し、6月18日には「被定忠常追討使事」(『小記目録』十七 臨時七)られた。これを受けて6月21日に宮中での陣定において「居住下野(ママ)平忠常」(『左経記』万寿五年六月廿一日條)の追討使が選定されることとなる。追討使の選定は「頼信、正輔、直方、成道」(『小記目録』十七 臨時七)の四名が候補に挙がり、「上達部申、伊勢前守頼信朝臣堪事之由」だったが、「而仰以右衛門尉平朝(臣)直方、志中原成道等共検非違使、可遣之由、右大弁奉勅伝宣、則仰史」(『左経記』万寿五年六月廿一日條)と、検非違使の右衛門少尉平直方、右衛門少志中原成道が選ばれた。検非違使が追討使とされたのは、忠常を検非違使の通常任務である追捕で対応可能と判断されたためとみられ、これに東海道・東山道諸国からの兵士及び兵粮の協力を付けて、忠常を「搦捕」ことを主任務として東国へと派遣されたのであった。
ところが、直方等の追討使は二年を経過しても忠常を捕えることができず、長引く戦いによる兵粮不足及び諸国から徴収した物資の浪費が続き、ついには兵站を維持することができなくなった。目立った戦功も挙げられぬままに、長元3(1030)年9月2日、「仰甲斐守源頼信并坂東諸国司等、可追討平忠常状、依右衛門尉平直方無勲功、召還之」(『日本紀略』長元三年九月二日條)と、頼信に平忠常追討が指示されると同時に、追討使だった右衛門尉平直方には召還の命が下されたという。具体的な宣旨が下されたのは9月6日で、「頭弁(蔵人頭源経頼)」が右大臣実資へ「甲斐守頼信、殊給官符国々相倶可追討忠常事」等五通の宣旨(及び宣旨目録)を持参している(『小右記』長元三年九月六日條)。
9月11日、「甲斐守頼信」は実資に「絲十絢、紅花二十斤」を志した(『小右記』長元三年九月十一日條)。忠常追討使への起用に対する礼か。翌9月12日、実資は右大弁源経頼が「持来給甲斐守頼信官符」等の案を関白頼通に覧せ、「可清書之由」の指示を受けている(『小右記』長元三年九月十二日條)。
9月23日、実資は頭弁経頼が持参した「給甲斐守頼信、追討忠宗(ママ)之官符草」を検見して返し、清書するよう指示を出した(『小右記』長元三年九月廿三日條)。
長元4(1031)年正月6日、任国甲斐に在国中の甲斐守頼信は「申治国加階事、可令外記勘申者」として「今日入眼請印」し、宣旨が下されて、頼信は「従四位下」に叙された(『小右記』長元四年正月六日条)。こうした中で、頼信は忠常に対して水面下で交渉していたと思われ、4月25日、「甲斐守頼信、申上忠常将参由事」(『日本紀略』長元四年廿五日條)と見え、忠常が頼信のもとに参じた一報が京都に参着している。その後、頼信が「権僧正(尋円)」へ送った書状が関白頼通に披露されたのだろう。4月28日、関白頼通は参内の際、同道した右大弁源経頼に「甲斐守頼信、送権僧正許書」を見せている(『左経記』長元四年四月廿八日條)。
●『権僧正書状』(『左経記』長元四年四月廿八日條)
5月20日には「常陸介兼資」からも忠常帰降の報が右大臣実資に届けられている(『小記目録』長元四年五月廿日条)。
藤原中正―+―藤原安親―+―藤原為盛――――藤原親国――――藤原親子
(摂津守) |(参議) |(越前守) (大舎人頭) (白河院御乳母)
| | ∥
| | ∥――――――――藤原顕季
| | 藤原隆経 (修理大夫)
| | (美濃守)
| |
| +―藤原守仁――――藤原尚賢――――藤原兼資
| (山城守) (越後守) (常陸介)
|
+―藤原時姫 +―藤原頼通
∥ |(関白)
∥ |
∥――――+―藤原道長――+―藤原彰子 +―後一条天皇
藤原兼家 |(関白) ∥ |
(関白) | ∥ |
| 円融天皇 ∥―――――+―後朱雀天皇
| ∥ ∥
| ∥―――――――一条天皇
| ∥ ∥
+―藤原詮子 ∥
|(東三条院) ∥
| ∥
+―藤原道隆――+―藤原定子
|(関白) |(皇后宮)
| |
+―藤原道兼 +―藤原伊周
(関白) |(内大臣)
|
+―藤原隆家
(中納言)
ただし、忠常の出頭に際しては「降順状」はなかったようで、6月6日か7日頃に右大弁経頼のもとに届けられた「自甲斐守送忠常帰降之由申文」は「而依不副忠常降順状」であり、6月7日、経頼は頼信に「早可上之由示送了」と指示を下すとともに、甲斐国解も「副彼状可付奏者也」とした(『左経記』長元四年六月七日条)。頼信の申文は「自美乃国大野郡送之由」とあり、この時点で「兼又忠常従去月廿八日爰重病、日来辛苦、已万死一生也、雖然相扶漸以上道」(『左経記』長元四年六月七日条)とあるように、忠常は5月28日から重病に陥っており、瀕死の状態ながら頼信が扶助しながらなんとか美濃国大野郡まで到達した旨が記されていた。
ところが6月11日、経頼のもとに「修理進忠節」が訪れた(『左経記』長元四年六月十一日条)。忠節のもとに「忠常子法師、去年相従甲斐守頼信朝臣、下向彼国」が「而只今京上」して報告するには、「忠常、去六日、於美濃国野上と云所死去了、仍触在国司、令見知并注日記、斬首令持彼従者上道者、又且注此由、可被申事由」(『左経記』長元四年六月十一日条)という。忠常が6月7日に美濃国野上で病死したため、頼信は国衙の在国司に命じてこれを見知ならびに日記に注させた上で斬首し、その首を忠常従者に持たせて上洛させる(実際は16日に頼信が携えて入京する)、という報告である。 これを聞いた経頼は「驚此告」き、「以前日、所送之忠常帰降之由申文、付頭弁令奏、是死去之由不申、以前可急也(先日、送られてきた忠常帰降の旨の申文を、頭弁経任に付して奏上させたが、これは忠常が死亡したということは申していない。以前から急ぐべきだった)」と述べている。なお、忠常死去の情報は同日に右大臣実資も「降人忠常死去事」(『小記目録』長元四年六月十一日条)と共有している(ただし、小右記本文(同日記録は散逸)に実資が後日追記し、目録時には同日のこととされた可能性もある)。
翌6月12日午後、宮中から退出した経頼のもとへ「修理進忠節」が訪れて「甲斐守消息」を渡している(『左経記』長元四年六月十二日條)。披いて見ると甲斐守頼信の「忠常死去国解」であった。この国解に副えて「副美乃国司返牒并日記等、又忠常降順状一枚同加送、是前日依遺取所送也」が送達された(『左経記』長元四年六月十二日條)。「忠常降順状」について京都からの書状が届けられたのは忠常死去ののちであることから、頼信が書いたものであったろう。
●『甲斐国解』(『左経記』長元四年六月十二日條)
経頼はこれら頼信消息、甲斐国解、美濃国司返牒、日記、忠常降順状を持って再度参内し、関白頼通に「令御覧此文等」した上で、頭弁経任に「為令奏聞送頭弁許」った(『左経記』長元四年六月十二日條)。
忠常が死亡した場所については、「美濃国野上と云所」(『左経記』)、「美濃国山縣」(『百錬抄』『扶桑略記』)、「美濃国蜂屋庄」(『千葉大系図』)とまちまちであるが、頼信が大野郡からの書状を発した時点で、厚見郡、山縣、蜂屋庄はすべて東側に位置していることから、美濃国不破郡野上が死去の地としては適当であろう。「野上」は国府にほど近く、美濃国の在国司による実検が行われたと思われる。現在、「しゃもじ塚」と呼ばれる伝忠常墓が野上(関ケ原町大字野上382-1)に祀られている。
| 没地 | 現在地 | 資料 |
| 美濃国厚見郡 | 岐阜市の一部 | 『左経記』 |
| 美濃国野上 | 不破郡関ヶ原町野上 | 『左経記』 |
| 美濃国山縣 | 山県市、岐阜市・関市の一部 | 『百錬抄』『扶桑略記』 |
| 美濃国蜂屋庄 | 美濃加茂市蜂屋町 | 『千葉大系図』 |
なお、忠常の死から百六十年ほどのちの建久6(1195)年12月12日、千葉介常胤が「老命、後栄を期し難し」として「警夜巡昼の節を励まし、連年の勤労を積む。潜かにその貞心を論ずるに、恐らくは等類無きに似たり」と、恩賞を求める「款状」を頼朝に提出した(『吾妻鏡』)。この中で常胤は「殊に由緒あり」として「美濃国蜂屋庄」の地頭職を望んでいるが、常胤が伝えたこの「由緒」は、平忠常の葬地だった可能性があろう。結局、蜂屋庄は「故院の御時、仰せに依りて地頭職を停止」した荘園であり、頼朝も如何ともしがたい土地である旨を伝え、「便宜の地を以ちて、必ず御計らい有るべきの旨」を記載した書状を遣わしている。
翌6月13日、「兼光出家事有与忠常同意之聞」した。「兼光」の具体的な姓は記されないため、該当者を確定できないが、実資が記し留める程の人物であるとすれば、藤原秀郷の孫の藤原兼光の可能性が高いだろう。「兼光」は忠常との繋がりが予てより噂されており、この前年の長元3(1030)年6月23日、右大弁源経頼のもとへ届けられた「追討使直方并上総武蔵国司言上解文」によれば、追討使平直方らは「忠常如言上不知在所者」(『小右記』長元三年六月廿三日条)だった際、「可令兼光申忠常在所歟、直方解文云、忠常、志直方之雑物兼光伝送、仍可知彼在所者」(『小右記』長元三年六月廿三日条)と、忠常が「直方之雑物(具体的には不明だが戦利品か)」を京都の「兼光」に伝送していることから、「兼光」が「可知彼在所」として「可令兼光申忠常在所」とされている。
6月14日、忠常の首級について「帰降者首、可梟哉否事」(『小記目録』十七 臨時七 追討使事)が議論されている。その二日後の6月16日、「頼信朝臣、梟平忠常首入京」(『日本紀略』長元四年六月十六日条)、「甲斐守頼信、随身忠常首入洛事」(『小記目録』十七 臨時七 追討使事)した。
6月27日午の刻、右大弁経頼が参内し、右大臣実資もまた参入した(『左経記』長元四年六月廿七日条)。この陣定では、平忠常の乱に際し、当初の追討使であった左衛門尉平直方を国司として支えた父・上総介平維時の「被停所帯職」の辞書を「如申状」と許可した。また「甲斐守源頼信、進忠常帰降之由申文、并常安降状忠常法名也、忠常死去之由解文、并美乃国司等実検日記等、被下云、頼信朝臣令帰降忠常之賞、可有哉否、又忠常男常昌、常近、不進降状、執可追討哉否之由、可令申者、次第見下了」(『左経記』長元四年六月廿七日条)と、忠常の子「常昌常近」は各々降順状を提出しなかったようで、その後追討の対象とすべきか陣定の議案とされた(『左経記』長元四年六月廿七日条)。
| 右大弁源経頼 | 頼信朝臣、令帰降忠常之賞、尤可被行也、但於其法者、先符云、随其状可給官位者、先被召問頼信朝臣、随彼意趣可被量行歟、又、忠常男常昌、常近等不進降順状、其身雖死去、於男常昌等者未降来、何黙被免哉、須任先符、執被追討也、而前使直方時、坂東諸国多属追討、衰亡殊甚云々、重遣使乎、若賜早可撃之符、偏経営此事之間、諸国弥亡、興復難期歟、暫被優廻、頗興復之後、左右可被行歟者 | 頼信朝臣が忠常入道を帰降させた賞については、まことに行うべきである。ただ、法に従うならば、先の追討官符には「状況に応じて官位を与えるべし」とあるので、まず頼信朝臣を召して意向を聞き、それに基づいて行賞の程度を決めるべきか。また、忠常の子の常昌、常近はいまだに降順状を提出していない。忠常入道はすでに死去しているとはいえ、その子常昌らはまだ降伏していない。どうして黙って免ぜられようか。やはり先符に従い、追討を行うべきである。ただし、前使直方の時に坂東諸国の多くが追討に加わり、衰亡が非常に甚だしい。もしも再び追討使を派遣して早々に攻めよと命じれば、国衙は追討に加わることとなり、諸国はますます荒廃し、復興は難しくなるであろう。したがって、しばらくは猶予を与え、国がある程度復興した後で追討すればよいだろう |
| 左大弁藤原重尹 | 頼信朝臣賞、同余詞、但常昌等事、為造意首忠常已以帰降、常昌等是従也、雖不被追討、有何事哉者 | 源頼信朝臣への賞については、私(経頼)と同意見だった。ただし、常昌らの件については、首謀者の忠常がすでに帰降し、常昌らもまたこれに従った。追討しなかったからといって何の差し支えがあろうか |
| 左兵衛督藤原公成 | 頼信朝臣賞事、同下官申旨、但於常昌等事者、常安降伏頗見男等降帰気色之中、忠常於途中死去、獄禁者遭父母喪之時、給其暇云々、況未被禁者哉、被優免有何事哉 | 源頼信朝臣への賞については、私(経頼)と同意見だった。ただし、常昌らの件については、常安の降順状にその子らの降伏も記されている。忠常は途中で死去しているが、獄に繋がれている者でも、父母の喪に遭えば暇が与えられる。まして禁獄されてもいない者であれば猶更であろう。常昌らを宥免することに何の問題があろうか |
| 新中納言以上 | 被申之趣、大略同余詞 | 新中納言以上が申される趣は、おおよそ自分と同じであった |
このように、陣定出席の公卿の大半は、頼信への行賞と常昌等の追討について経頼同様の意見だったようだ。なお、「新中納言」については、長元2(1029)年正月24日に権中納言となった藤原経通、藤原資平、藤原定頼のいずれかとなろう(『公卿補任』長元二年)。彼らはいずれも小野宮流藤原氏に属する公卿である。この結果を頭弁経任が覆奏し、「依多定申者」との宣旨が下された(『左経記』長元四年六月廿七日条)。
長元5(1032)年2月8日、美濃守に遷任する(『類聚符宣抄』巻八)。
●『源頼信謹言』(『類聚符宣抄』巻八)
それ以降、頼信の具体的な活動はうかがえず、永承3(1048)年9月1日に卒した(『尊卑分脈』)。没年齢は六十歳(『尊卑分脈』)、七十五歳(『系図纂要』)。なお、生年が『諸家系図纂』の安和元(968)年(元服記事から逆算)すると、永承3(1048)年卒去で八十一歳となる。法名は蓮心(『系図編纂』)。